 | ||||||
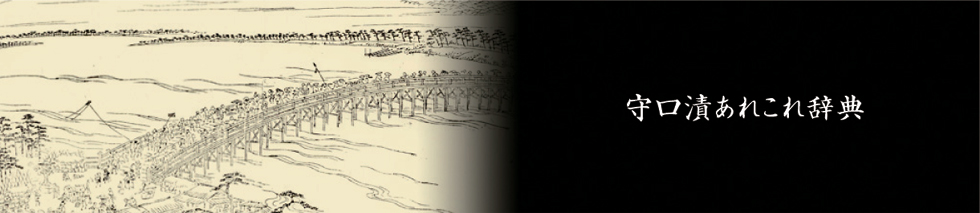 |
||||||
|
||||||
| 1.萱津神社の由来と漬物の起源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
その後、土地の人々がこの神前にウリ、ナス、大根等の初なりを供えた。当時このあたりは海浜でもあったので、海からとれた塩もお供えするようになり、これらをカメに入れてお供えしたところ、神の思召しか、程よい塩漬けになり、当時の人々は雨露に当たっても変わらない不思議なその味を神からの賜りものとして、遠近を問わず頂きに集まり、万病を治すおまもりとしたとあり、これがわが国の漬物の始まりであるといわれている。 景行天皇の御子日本武尊御東征の道すがら当社にご参拝になり、この時、村人がこの漬物を献上して長途の旅情をお慰めするとともに、霊験あらたかなことどもをお話し申し上げたところ、尊は非常にご感慨深げに「藪二神物(やぶにこうのもの)」と仰せられたと伝えられ、その名は愈々(いよいよ)広く世間に伝わり、いつ頃からか「香の物」とも書くようにもなった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.漬込神事と熱田神宮奉献 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尊が熱田の宮にお鎮まりになった後、尊を忍び村人は格別ゆかりの深いこの「香の物」をお供えした。以来これが恒例の行事となって今日まで悠久2000年になんなんとする長い間、熱田神宮の歳旦・祈年・新嘗(今日では元旦祭・春祭・秋祭といわれている)及び例祭の四祭に特殊神饌として奉献されてきた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.皇室・幕府と香の物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇室・幕府とのゆかりも深く、旧幕府時代には、この「香の物」を度々皇室に献上したと伝えられ。また、当社へは、室町初期の国守萱津左京大夫頼益が神田(みとしろ)六十貫を寄進した。また、元和9年、藩主徳川義直は「香の物領」として元高五石八斗余の地を献進し、明治初年まで続いた。畏くも昭和・大正両陛下御即位式奉祝のため献上を願い出た折もその都度御嘉納の光栄に浴した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.漬物祖神萱津神社奉賛会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.珍本「うろこやの黒本」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 萱津神社所蔵の「黒本」は宝暦8年、江戸の「うろこや」が出版した僅か2冊、10ページにも満たない絵本で、壬申の乱の時、大海人皇子(後の天武天皇)の夫人で、後の持統天皇が、萱津に滞在され、漬物三昧の生活をおくられたという内容の珍本である。 この頃、萱津には、援軍尾張初代国司小子部■(金へんに且という字)鈎(ちいさこべさびち)が2万余りの兵を率い参戦しており、安全地帯であった。吉野を発って桑名へ出られた大海人皇子は、美濃不破の決戦場へ向かわれる前に、持統天皇をこの地に避難させられた。この假宮(かりのみや)での生活ぶりが漬物一色である。朝夕の食事は全て野菜。持統天皇も殊更これらの漬物を好んで召し上がられたが、漬物の手入れに追われる侍女等は大変な苦労であった。 「時々手を入れてかき回さねば、くさくなりたがる」とあり、この頃の漬物は、単純な塩漬ではなく、糠(ぬか)味噌漬であったことがうかがわれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※以上の1~4の文章は萱津神社青木宮司の許可を得て「漬物祖神 ゑんむすびの神 萱津神社について」から漬物に関する部分を抜粋し掲載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○萱津神社の概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (愛知県神社名鑑より) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||




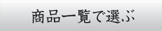
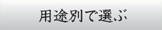

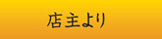

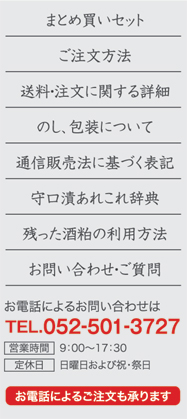
 個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いについて





